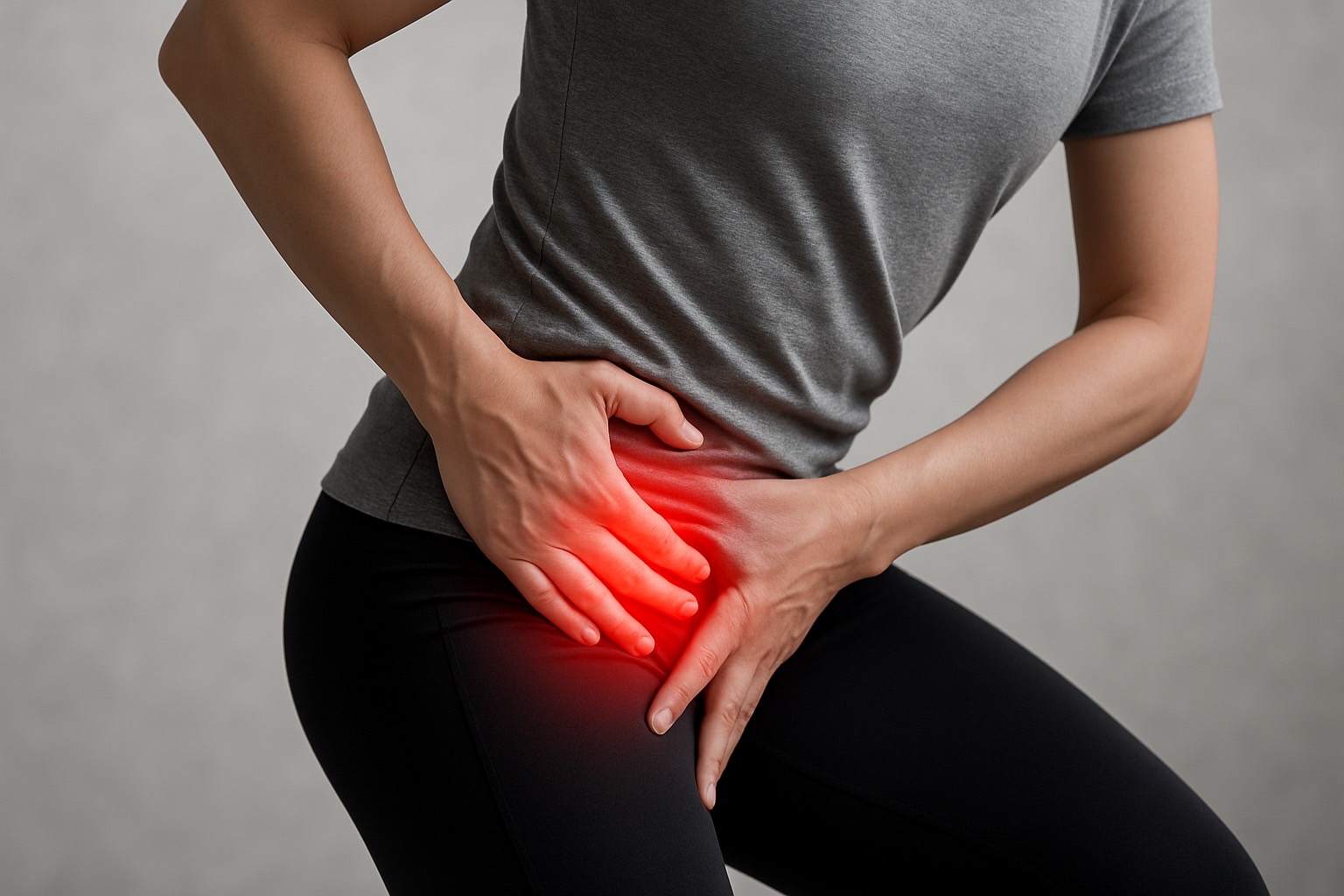⸻
はじめに
「股関節が痛い」という訴えは日々治療を行う中でよくあります。特に歩行時や立ち上がりの動作、階段の昇降など、日常のささいな動きの中で痛みを感じる方は多いでしょう。
そのとき、多くの人が痛みのある股関節そのものに注目し、「関節が擦れてるのでは?」「筋肉が炎症を起こしてるのでは?」と考えがちです。
しかし、実際の臨床現場では、「痛みがある場所が原因ではないケース」が数多く見られます。
これは、「筋膜」(きんまく)という“筋肉を包む膜”のつながりや、「骨盤と股関節の構造的関係」に深く関わっています。
本記事では、理学療法士の視点から、
「痛みが出ている場所=原因とは限らない」
「反対側の張りや引っ張りが、症状側に影響を与える」
という事実を、筋膜・骨盤・神経・代償運動の視点から徹底的に解説します。
⸻
痛みのある側に“原因がない”ことは多い
例えば、症状が出ている側の股関節(ここでは「症状側」と呼びます)をいくらマッサージしても、痛みがすぐ戻ってしまう。
または、腸腰筋や内転筋にアプローチしても改善しない。こういったケースは決して少なくありません。
それはなぜかというと、身体は「つながって動いている」からです。
股関節は、骨盤・仙骨・腰椎・体幹などとの複雑な連動の中で動いています。
その中でも特に大きなカギとなるのが、「反対側(対側)の腰部や仙骨からの影響」なのです。
⸻
対側の腰が張ることで、仙骨が引っ張られるメカニズム
まず理解しておきたいのが、「筋膜」と呼ばれる組織の存在です。
筋膜とは、筋肉や内臓、骨などを覆う「膜状の組織」で、全身を立体的につなぐネットワークのような構造をしています。
とくに腰の筋肉(腰方形筋、腸肋筋、多裂筋など)の周囲には、「胸腰筋膜(きょうようきんまく)」というとても強靭な筋膜があります。
この筋膜は背中や骨盤、そして仙骨(せんこつ:骨盤の中央にある逆三角形の骨)にまで広がっており、まさに“身体の中心を包む膜”です。
対側の腰部が張って硬くなると、その筋膜を介して仙骨が「斜め後方」に引っ張られるようになります。
つまり、筋肉の張りがある側の腰から仙骨が引かれ、仙骨がねじれながら前傾・回旋し、骨盤全体のアライメントが乱れていくのです。
⸻
骨盤のゆがみが股関節に与える影響
仙骨がねじれると、左右の腸骨(ちょうこつ:骨盤の羽のような部分)にもズレが生じます。
このとき、対側の腸骨が前に出て下がり、症状側の腸骨が後ろに引かれるという連動が起きやすくなります。
(=骨盤の「回旋+側方シフト」)
すると、症状側の股関節は、
・後方(伸展位)に引かれた状態
・軽度の外旋・外転方向への制限
・屈曲・内旋がしにくくなる
という「機能的なズレ」が生じやすくなります。
⸻
股関節が“伸展+外旋”気味になると何が起こるか
このように、股関節が機能的に「伸展+外旋」方向に誘導されてしまうと、
脚を前に振り出す(=股関節を屈曲する)ときに、本来使われるべき筋肉がうまく働かなくなるのです。
例えば、
・腸腰筋(ちょうようきん):股関節を前に持ち上げる主働筋
・大殿筋(だいでんきん):股関節の安定・伸展に関与
・内転筋群(ないてんきんぐん):骨盤を支えるバランサー
これらがうまく使えないと、体は別の筋肉に頼り始めます。
その筆頭が、縫工筋(ほうこうきん)です。
⸻
縫工筋とは?なぜ代償的に使われすぎるのか
縫工筋は、太ももの前面を斜めに走る細長い筋肉です。
骨盤の前側(上前腸骨棘)から、膝の内側(鵞足部)までつながり、
股関節の「屈曲・外旋・外転」、膝の「屈曲・内旋」に働きます。
本来は補助的に使われるこの筋が、
・腸腰筋の代わりに脚を上げる
・内転筋の代わりに股関節を安定させる
などの役割を担わされると、オーバーユース(使いすぎ)になり、筋緊張・疲労・牽引痛が起こりやすくなります。
⸻
縫工筋の過剰使用で起こる症状
・股関節前面(とくに鼠径部)の詰まり感・引っかかり
・股関節を曲げたときの「引っ張られるような痛み」
・膝の内側(鵞足部)の鈍い痛みや違和感
・脚が振り出しにくい、歩行が重たい感覚
・長く歩くと脚がだるくなる、階段でつまづきやすい
これらはすべて、縫工筋の代償使用によって起こる“隠れた痛み”の可能性があります。
⸻
筋膜ラインのつながりで見る“身体の連動”
アナトミートレインという筋膜理論では、筋膜は「ライン(連鎖)」として全身をつないでいます。
とくに今回関係が深いのは:
・バックファンクショナルライン
→ 広背筋 → 胸腰筋膜 → 反対側の大殿筋 → 大腿筋膜張筋・腸脛靭帯
・ディープフロントライン
→ 横隔膜 → 大腰筋 → 骨盤底筋群 → 内転筋 → 足底
このように、対側の背中~骨盤の張りが、症状側の股関節前面に連動してくる構造が明確に存在します。
⸻
セルフケアの方法|マッサージガンとストレッチの併用
痛みの出ている股関節に直接アプローチするのではなく、まずは対側の腰や仙骨周辺を緩めることが重要です。
【マッサージガンの使い方】
① 対側の腰の筋肉(腸肋筋・腰方形筋周辺)に軽く当ててゆっくり動かす(20〜30秒)
② 仙骨周囲に軽く当てて、振動を伝える(押しすぎない)
③ 使用後はゆっくりとストレッチ(対側殿部・体幹回旋)を組み合わせる
【ポイント】
筋肉に対して垂直ではなく、角度をつけて当てると効果的
【注意点】
・炎症が強いときは避ける
・背骨の真上や骨盤の骨には直接当てない
・深く押しすぎない(振動で十分)
⸻
トレーニングで再発予防を
対側の腰を緩めた後は、股関節や体幹を安定させる筋肉の再教育が不可欠です。
・ヒップリフト(大殿筋)
・サイドプランク(中殿筋+体幹)
・ニーアップ(腸腰筋)
・スクワット(バランス強化)
・立位での体幹回旋運動(胸腰筋膜の左右バランス)
これらを継続することで、「左右の張力差」が整い、股関節の可動域や安定性が戻っていきます。
⸻
まとめ|痛みの場所ではなく「動きの流れ」を診る
股関節が痛いとき、そこに原因があるとは限りません。
対側の腰の張り、仙骨のねじれ、骨盤の傾き、筋膜のテンション…。
これらがすべて連鎖しながら、結果的に“痛みが出やすい状態”をつくり出しているのです。
あなたの身体が発する“違和感”を無視せず、身体全体の流れとつながりに目を向けること。
それが、本当の意味での予防・回復への第一歩です。